はじめに
脳性麻痺は、出生前後の脳の損傷によって引き起こされる運動障害です。リハビリは、運動機能の改善や日常生活の自立を支援する重要な役割を果たします。本記事では、脳性麻痺に対する一般的なリハビリについて解説します。
動画解説は↑コチラの画像をクリック
1. 脳性麻痺と神経発達療法(ボバース・ボイタ)
かつて、脳性麻痺のリハビリには神経発達療法(NDT)が広く用いられていました。代表的なものとして、ボバース法やボイタ法があります。
- ボバース法:運動パターンの正常化を目的とし、姿勢や動作を誘導することで神経の可塑性を促す手法。
- ボイタ法:特定の反射を刺激することで運動機能を回復させるアプローチ。
これらの方法は長く実施されてきましたが、近年では科学的なエビデンスに基づいた新しいアプローチが主流になりつつあります。
2. 脳性麻痺と現在のリハビリ
近年の研究により、NDT(ボバース・ボイタ)よりも効果的なリハビリ方法が注目されています。現在主流となっているリハビリ方法には、以下のようなものがあります。
- CI療法(Constraint-Induced Movement Therapy):麻痺していない側の手を制限し、麻痺側を集中的に訓練することで機能回復を促す。
- 両手・上肢集中訓練(HABIT):両手を協調的に使う動作を繰り返し練習し、運動機能を向上させる。
- 目的志向型トレーニング(Goal-Oriented Training):日常生活に必要な動作を目標に設定し、実際の動作を通じて機能改善を目指す。
- ホームプログラム:家族が日常生活の中で継続的に行える訓練を取り入れることで、効果を最大化する。
これらの方法は、実際の活動を重視し、運動学習の観点から機能改善を促す点で、従来のNDTよりも優れた効果があるとされています。
3. 脳性麻痺のリハビリ注意点
脳性麻痺のリハビリでは、以下のポイントに注意することが重要です。
- 無理に正常な運動パターンを押し付けない:身体機能に見合った効率的な動作を優先。
- 適切なポジショニング:股関節脱臼や拘縮を予防するため、正しい姿勢を維持することが大切。
- 遊びを活用する:ボール投げ、マット運動、トランポリン、バランス練習など、楽しみながら運動機能を向上させる方法が効果的。
- 環境設定:子供が好奇心を持って遊べる環境づくりを
特に、重症児(GMFCSレベルV)では、立位・歩行が目標とならない場合もありますが、支持(介助)立位や自発的な移動を促すことも大切です。
終わりに
脳性麻痺のリハビリは、最新の科学的エビデンスに基づいた方法を選択することが重要です。従来のNDTに頼るのではなく、CI療法やHABITなど、より効果的なアプローチを取り入れることで、運動機能の向上が期待できます。専門家と相談しながら、最適なリハビリプランを実施していきましょう。
#京都 #脳梗塞 #脳出血 #片麻痺 #運動麻痺 #リハビリ #自費リハビリ #歩行 #脳性麻痺 #オステオパシー #京都オステオパシー #四条大宮 #手の麻痺 #手指の麻痺 #姿勢 #手足の緊張 #子供の脳卒中 #子供の麻痺
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
京都オステオパシーセンター:OQ
〒604-8366 京都府京都市中京区七軒町466
最寄駅:阪急大宮駅 徒歩2分
京都 中京区 めまい、頭痛、産前産後、不妊、
マタニティ整体、呼吸器、子供の発達、
脳卒中後遺症 人工関節、
慢性的な痛み(肩こり・腰痛・変形性膝関節症
変形性股関節症など)
受け付け時間:9時~21時(完全予約制)
坂田:日・祝 休み
大村:土 休み
問い合わせ先
【坂田】
LINE: https://lin.ee/clbSLGg
電話:075-822-3003
【大村】
LINE: https://lin.ee/XnR5zpR
電話:080-3850-1264
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この記事に関する関連記事
- 子供の靴を定期的にチェックしましょう
- 医療保険では限界を感じていた 脳卒中 Case3
- 脳卒中 手の麻痺 家庭での電気刺激の活用
- 脳卒中 手の麻痺 振動刺激 家庭用
- 脳卒中後遺症 歯軋りを軽減する方法
- 40-50代にもおこる 脳卒中のリスクとは
- 40-50代にも起こる脳卒中のリスクとは
- 退院後の脳卒中のめまい セルフケアについて
- 脳卒中の回復と栄養
- 脳卒中Case2 右片麻痺・失語症 口コミ紹介
- 脳性麻痺に対するオステオパシーのエビデンス
- 脳卒中 片麻痺 走る練習について
- 最新!脳卒中を回復する薬?? edonerpic maleate
- 脳卒中 ケース1 右半身麻痺 高次脳機能障害 半側空間無視
- 脳梗塞後 ぶん回し歩行 原因 痙縮について知ろう
- 脳卒中後 歩き方が気になる
- 「脳梗塞後のぶん回し歩行 可動域制限の問題とセルフケア」
- フットの日 僕らの足育~人生を歩む足を育む~」オンラインイベントの インタビュー
- 脳梗塞の方へ ぶん回し歩行の特徴と原因について
- 脳梗塞後に多い身体の悩みBEST3
- 脳梗塞 脳出血 特に痛みが出やすい肩関節 3つの対策
- 手指の麻痺状態の確認 ブルンストロームステージとは?
- 手指の握り込みについて 無理に伸ばすと逆効果??
- 脳卒中後の後遺症「小脳性認知情動症候群」
- 脳梗塞・脳出血の方にストレッチをおすすめする理由について
- 脳卒中後の歩行練習 実はとっても省エネ 正常歩行について
- 脳卒中後の歩行回復に必要な神経学的な側面
- 脳梗塞脳出血後の動きをスムーズにする3つのポイント
- 脳卒中後遺症の日常を輝かせるセルフケア術
- 脳梗塞 再発予防 手助けの鍵となる栄養素は?
- 脳梗塞・脳出血後遺症 半側空間無視に対するご家族の注意点
- 脳梗塞・脳出血 半側空間無視について
- 脳梗塞・脳出血 最新ロボット機器3選
- 脳梗塞 脳出血 手の麻痺 最新機器 「まいリハ」
- ここまで進化している 脳卒中後の最新リハビリ
- 鳥山明さんを襲った 急性硬膜下血腫とは??
- 脳卒中との違いは? トルソー症候群について解説します
- 脳梗塞 脳出血 再発予防 抑えておきたい5つのポイント
- 脳梗塞 脳出血による小脳性運動失調は改善するのか?
- 脳梗塞・脳出血 小脳性運動失調おすすめの運動3選
- 脳卒中後の運動麻痺克服の秘訣
- 脳梗塞・脳出血の方にストレッチをおすすめする理由とは?
- 脳卒中後 うつ伏せのメリットについて
- 脳梗塞の脳出血後 首の痛み 肩こり おすすめ体操3つ
- 脳梗塞・脳出血後 首が痛い3つの原因について
- 脳梗塞 脳出血 姿勢の特徴「外骨格化」とは??
- 脳梗塞 手の麻痺 最新機器 パワーアシストハンドについて
- 脳卒中後の歩行の回復について 神経学的な側面について解説
- 脳卒中/発症3年経過 施術後インタビュー
- 脳卒中後遺症 脚のしびれ
- 脳卒中後の上肢麻痺と歩行障害の関係
- 脳卒中後遺症 自費リハビリ 期間限定 無料体験実施中
- 脳卒中の方にストレッチをオススメする理由
- 脳卒中の方から息子へプレゼントをいただきました
- 脳卒中の方にストレッチをおすすめする理由
- 脳卒中後の方 必見! 自費リハビリのメリット
- 意外な脳卒中後の身体の変化について
- 鳥山明さんを襲った 硬膜下血腫とは
- 脳卒中後遺症 高次脳機能障害 周囲はどう手助けすべき?
- 脳卒中後遺症 小脳性認知情動症候群とは
- 脳卒中後の動きを良くする3つの必須ポイント
- 小児 脳卒中 手足の緊張を解く鍵は?
- 脳出血/50代/男性/非麻痺側の肩が上がらない!?
- まいリハ ついに納品!
- 脳梗塞 手指の握り込み 無理に伸ばすと逆効果
- 脳梗塞 手の麻痺の方 必見! パワーアシストハンド 新型Ver まいリハ
- 脳卒中後の首の痛みにオススメの体操3選
- 脳卒中後 首をグルグル回すのは逆効果!?
- 脳卒中後あるある 首の痛みなぜ起こる?
- 脳卒中後の歩行練習 実はとっても省エネ! 正常歩行
- 脳卒中後の歩行練習 まずは正常歩行を知ろう
- 神経学的な側面を解説 脳卒中後の歩行回復
- 脳卒中後遺症から脱却 日常を輝かせるセルフケア術
- オンライン活用の時代❕ 脳梗塞後の遠隔リハビリについて
- 脳梗塞・脳出血後の歩行障害 あなたはどれにあてはまる❔
- 発症後不安になりがち、、、脳梗塞 脳出血後の予後
- 脳梗塞 脳出血 「手足が硬まる痙縮」について
- 脳卒中以外の方にも見てほしい❗️ 『脳梗塞・脳出血後の復職』
- 脳卒中の痺れ 3つの原因と対策







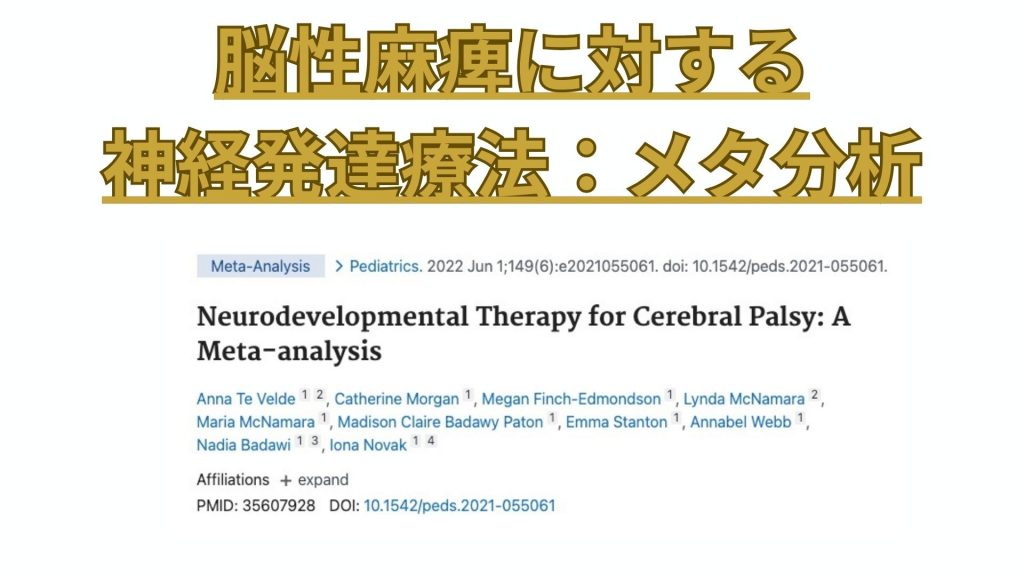
お電話ありがとうございます、
京都オステオパシーセンターOQでございます。